清酒の定義
財務省が国会に提出した酒税法改正案で、5月1日から清酒の定義が変わる可能性が…。
■改正案
次に掲げる酒類でアルコール度が22度未満のものをいう(1)米、米こうじおよび水を原料として発酵させて、こしたもの
(2)米、米こうじ、水および清酒かすその他政令で定める物品を原料として
発酵させて、こしたもの
(その原料中、当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む)
の重量の100分の50を超えないものに限る)
(3)清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
現行“酒税法”第3条第3項と変わった部分は、アルコール度が22度未満とされたことと、上記(2)の『当該政令で定める物品』、いわゆる副原料の使用割合が100%から50%に減らされたこと。
これにより、増醸酒(三倍増醸酒)は清酒ではなくなる。
ちなみに、使用できる副原料については、“酒税法施行令”第2条の規定、ならびに以下を…。
■増醸酒(三倍増醸酒、略して三増酒)
第2次大戦後、酒造用米の極端な不足により、1949(昭和24)年から製造されるようになった。
白米1tにつき2,400L(アルコール分30%換算)の調味アルコールを醪の末期に添加して上槽する方法で、米だけから生成すると見込まれるアルコール量の約2倍に相当する調味液を添加することになり、収量が約3倍となるのでこの名称がある。
調味液に使用できる物品は、アルコール、ぶどう糖、水あめ、乳酸、コハク酸、クエン酸、リンゴ酸、グルタミン酸ナトリウムに限られている。
また、三倍増醸に使用することができる原料白米の数量は、酒税法の承認基準によって使用する総白米数量の23%の範囲内となっている。
−【改訂 灘の酒用語集】より−
ただし、例によって、酒税法改正案の付則65条(清酒に係る経過措置)により…
今年5月1日以降の清酒の新しい定義に基づく清酒と増醸酒を混和する場合の取扱いは、アルコール度が22度未満で、副原料の重量が米の重量の50%を超えない酒類は、平成19年9月30日までの1年5カ月間は「改正酒税法に規定する清酒」とみなす。
という、逃げ道は残されている。
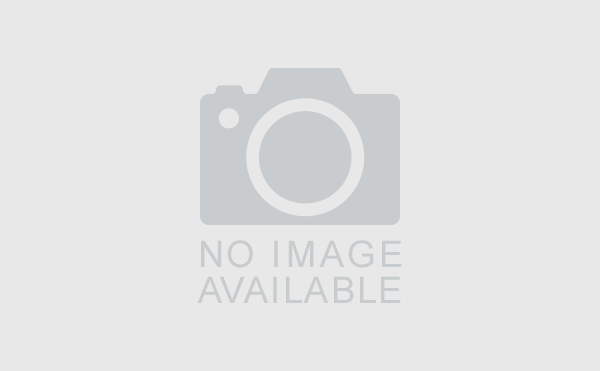
何故に逃げ道なんかが添えられているのでしょう?!
解せませぬ・・・。
でも「清酒」と表記できなくなったら
どういう表記になるんでしょうか。
普通に「増醸酒」と書かれるのかなぁ。
米の定義には踏み込めなかったのかなぁ…。
>まき子さん
増醸酒にしても酒税は納めているわけで、いわば納税者への配慮ってことでしょう。
改正案のままなら「その他の醸造酒」になるかと。
>nizakeさん
やっと三増酒が消えたとはいえ、まだ副原料の使用が許されていますからねぇ。
経済酒メーカーへの配慮といえば聞こえは良いけど、税金さえ取れれば、文化も技も人も、そして消費者の安全も、相変わらず“蔑ろ”にされたままってことかと…。
農水省や厚生省との絡みもあるにしろ、“自分の権益を守る”行政の都合が先で、誰のため、何のための法なのかという、基本的な思想が欠落したままですね。
先々、バカを見るのは消費者なのに…。
絶対に納得できないこと。液化仕込みの米粉は
「米」なのか「糖類」なのか?問題を先送りして
大手は面目を保った。中小の蔵は三増酒の普通酒が
圧倒的に多く、コスト高になり、困っている。
まだまだ味が「?」な日本酒は存在し続ける。
酒税が度数に関係なくなったことだけが朗報。
>Tankさん
云われそうな予感はあったけど…。(^^;
米粉・米糠は米じゃないです!! キッパリ。
『米、米こうじおよび水を原料として発酵させて、こしたもの。
ただし、米・米こうじは国産の玄米を精米したものに限る』
清酒の定義はこれだけで良いような…。
輸出もできない製法を認めることには、はなはだ疑問を感じます。
減反奨励金より、酒米を作ってもらって休耕地をなくしたほうが、農業も元気を取り戻せると思うのですが…。
ただ、酒税に関しては、基本的に製法をきちんと定めた上で、醸造酒・蒸留酒・混成酒に限らず、アルコール度数当たりの酒税とすることが、一番すっきりすると思っています。
>おやぢさん
御意。酒税法についての考え方はさまざまですね。小生は、醸造酒と蒸留酒は酒税法が違っても
構わない主義ですね。今回日本酒が果実酒と同じ
税法になりますが、純米酒ならこれで良いのでは?ワインのように「スティルワイン」「フォーティファイドワイン」「フレーバードワイン」と
分けて、酒税法が違うという形が良いと思って
ますけど。問題は「純米酒」と「本醸造」が
同じ税率であるということ。(あくまでも私見)
>Tankさん
ふぅむ、酒税に関してはいろんな側面がありますものね。
まずは製法を定義し、擬きをはっきり類別してからですね。
大量消費を煽るような“安ければ正義”は、酒類にそぐわないものでしょうから、
擬きにはむしろ高い税をかけるという結論が自然に生まれるような議論を期待したいですね。
今回の税改正で、発酵原料に糖類を使えるみたいですね、つまり液糖を投入すればアルコール添加と同様な効果が得られ、醸造アルコール添加を表記しなくても良いという、ザル法になる可能性を感じています。
精米歩合の低い「米原料100%」は、磨いてないから純米酒と名乗れない現状も何とかならないのかな?
>Jさん
どこのどなたか存じませぬが、ようこそ!! :-p
まだそこまでの情報を入手していないのですが…
アルコール添加と同様の効果とは、増量という意味で、ということでしょうか?
ちなみに、現行の“純米酒”表示には精米歩合の規定はありませぬ。(-"-)#