クレイマー
帰るといきなり老父から
「今飲んでいる酒、しょっぱいぞ。日付を見たら19年の詰めだし、なんでこんな酒、飲ませるんだ」
とお小言を頂戴した。
確かに塩のミネラル分を感じさせる酒に出会すことはあるけれど…
「あの酒が?」と追試しようにも「空じゃない!?」
その空の一升瓶からわずかに残った一垂れを杯に受けて…
 ■鯉川 特別純米 H19BY
■鯉川 特別純米 H19BY
老父母の定番酒♪
「へぇ〜、結構酸もあるし、まだ若いけど味乗りも案外早い」
という「うめぇじゃねぇか」きき酒を受けて…
「しょっぱかったとしたら、口の所為でミネラル分を異常に強く感じたんでしょ。それに、まっとうな酒はきちんと寝かせないとうまくならないから、一年や二年でガタガタいいなさんな」
とまるでビギナーに説明しているようなもの。
もっとも、大正後期生まれの老父が酒を飲むようになった歳には既にアルコールの添加(1939)が行われ、その10年後には糖類、そして挙げ句には酸味料まで加えられた、いわゆる三増酒の試験醸造がはじまったのですから、そうした酒しかなかった時代が人生の大半を占める訳でして、或る意味、最も不幸な世代の一人でありますな。
しかも、当地はアルコール添加された酒が今以て幅を利かせている土地柄ですから、米のうまみ・有機酸・熟成に対する古い常識を覆すのは容易ではありませぬ。
それにしても身内からクレイムを受けるとは思いませなんだ。
取りあえず石川杜氏の「間違いだらけの酒常識」を読んでもらいましょうか。(苦笑)
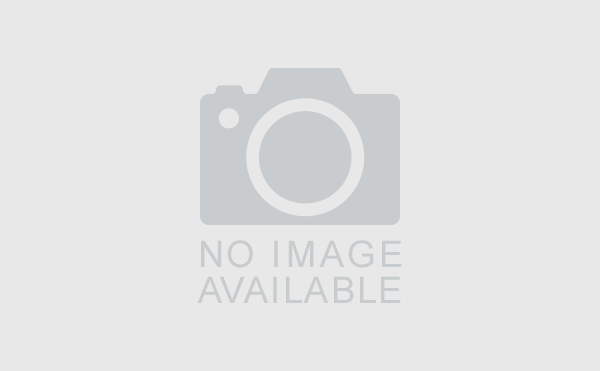
初めて「どぶ」を飲んだとき、非常に程度のいい天然塩をなめたあとのような、しょっぱさとうま味を感じました。それ以来、自分にとって、しょっぱさをおぼえる酒は、現在も楽しめ、将来はもっと楽しめるであろう酒、のように思っております。
*Yasuさん
そう、塩を連想させる味わいですけど、いいですよねぇ?
老父は最近でこそ巻き添えを喰らって(笑)主に県外酒を嗜んでいますが、
それまで何十年と飲んできた薄酒にベロが慣らされていますから、
こういううまみもあることを理解できないようです。
和が親ながら気の毒な世代だと思いますわ。
あたしんとこも同じですな。
もっぱら飲むのはパック酒と焼酎。あたしが家飲み用に買った酒も飲みますが、ことさらそれに執着しようとはしません。要は酔えればいいんだということ。戦争に行って、食糧難の時代をかいくぐり、生めよ増やせよということで自分の事はさておいて我々団塊の世代を育ててくれたんですから、考えてみれば一番可哀想な世代です。今団塊の世代のことが色々言われてますけど、団塊の親達(80代)をもっと取り上げるべきかと。
*とりしやさん
「酔えればいい」のはその世代だけでなく大多数の人にとっての現実ではないでしょうか。
ただ、親たちの世代のようにモノがあるだけで良かった時代ならいざ知らず、
今の世でもボロが罷り通ることには「ふざけんじゃねぇ〜!!」ですけど。
あの世代に比べたら、我々は遙かにヤワですね。(苦笑)