阿波をたずねて百九拾里
 「これの火入れ熟成酒が面白いんだけど…」
「これの火入れ熟成酒が面白いんだけど…」
と酒縁上の妹からお声が掛かったのは昨年の暮れのこと。
現物を拝見し、即、「お願いできますか?」となったものの、時期が時期ゆえ、お目にかからないままはじまったご縁。
先日、某お蔵を訪ねる際に「どうせなら」ともう一足伸ばして、ここまで出向くことに…。
夜通し走って遅い夜が明けた阿波の山中での第一声は「寒いっ!!」でした。 今年は出かける度に当地よりも寒さを味わう運命のよう。
 「道具も昔のをそのまま使っていますし、古いだけで何もありませんけど」
「道具も昔のをそのまま使っていますし、古いだけで何もありませんけど」
と造りの終わった蔵の中をご案内いただきました。今季はお嬢さんが戻って手が増えたとはいえ、造りのすべてをご夫妻だけでこなす基本は変わらず。
「今年も三本だけですわ」
とご当主は苦笑いされますが…
「お二人だけでよくぞ」
とあらためて感心してしまいます。
こういう造り手がいてくださるからこそ、我々は夜な夜なおいしいお酒を、それが当たり前のことのように飲んでいられる訳ですから。
 「昔の酒のままで良いと思いますよ」
「昔の酒のままで良いと思いますよ」
大正時代のものとされる “実験 清酒醸造法講義" を見つけたことが、今の “旭若松” へ変わる転機となったそう。
確かに、その後で変わったことといえば、アルコールや糖類の添加、そして挙げ句には酸味料まで。昨年の酒税法改正でやっと清酒の分類から外されたとはいえ、まだ残る三倍増醸酒の数々。
米不足の中で否応なしに副原料を使わざるをえなかった時代がとうに終わった現在まで、延々と続けられている紛いものづくりが、どれほどの造り手や飲み手を葬ってきたことか。
歴史的な背景があったにしろ、今の飲み手のほとんどが紛いものしかなかった時代に飲酒できる年齢を迎えたことが、相も変わらない日本酒の凋落、その最大の要因となったのではないでしょうか。
 最近の “旭若松” の酒質を「らしくない」と非難するかのような物言いも巷間目にしますが、ご当主曰く「近年、(メーターが)切れるようになった」ゆえのことかと。
最近の “旭若松” の酒質を「らしくない」と非難するかのような物言いも巷間目にしますが、ご当主曰く「近年、(メーターが)切れるようになった」ゆえのことかと。
でもそれは、甘残りがもたらす味の多さだけがウリではなく、キレも締まりもある酒になってきたということ。むしろ、それこそまっとうな酒でしょ!?
ただし、また飲み頃が遅くなりますけど…。
いずれにしろ、今年の三本の中で何をおすすめするか、それについては急いては事をし損ずる。楽しみは取っておいた方が大きくなると思いません?
てな訳で、もうしばし待たれよ♪
急、かつ、朝早い訪問にも拘らず快くお迎えいただき、お世話になりました。
松浦ご夫妻に心から感謝申しあげます。ありがとうございました。
ただ、おかげでもう一軒寄らなければならなくなったのは、まったくの計算外。X-)
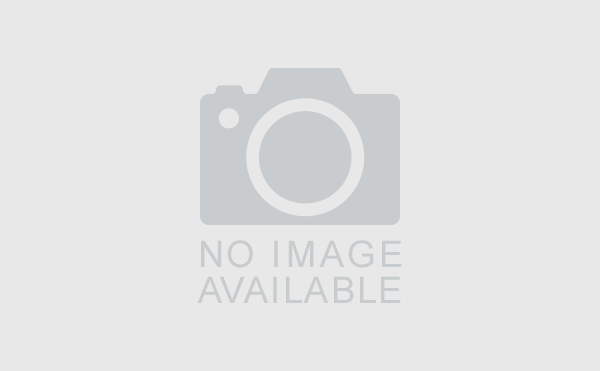
考えさせられました。まがい物が横行しているときに
飲酒年齢を迎えた世代から多分少し後ですが、入り口は
同じ状況だったと思います。主人は自分よりもうひとまわり
上、なので、もっと実感していると思います。
「もっと早くに、純米酒、燗、飲み頃、っていうことを知っていたら。
“まっとう”ということに、もっと早く気が付いていれば」と、
悔しそうに口にすることがあります。数多くの呑み手や作り手を葬って
きた、という一文に、胸が締め付けられました。
旭若松は、味が変わった、と私もはっきり思いました。批判も
やはり耳にしましたが、あのカツンとした感じ、私は好きです。
おやぢさんがそれを良しとしていると読んで、安心しちゃったです…^^;
などと言ってしまいましたが、精進、精進です。
「造り手、飲み手」でした。ごめんなさい(汗
変換すると「作」と「呑」の字がすぐ出る…(言い訳
切れが悪いという印象がなくなってきましたか、それはよかった。
To りえぞさん
神亀さんが全量純米に切り換えてまだ四半世紀。未だに「全量純米蔵」が稀である
ことを考えると…状況はほとんど変わっていないってことでしょ?
日本酒が日本酒であるためにも、早くボロ酒のない世の中にならないとねぇ。
そのための第一歩が「飲み手」がきちんとした舌を持つことだと思うのですが、
なかなか「酔えばいいだけ」の酒から抜け出そうとしませんな。
まっとうな造り手がいるのですから、次は売り手(飲食店・酒屋)が如何に伝えるか、
責任重大ですぞ♪
“旭若松”の変貌は我々がとやかくいう筋ではないと思いますよ。
でも、また飲み頃が先に延びたことは確かですから、それだけは痛い!! (苦笑)
To 煮酒さん
でしょ!? 喜ぶことであっても貶すことじゃないと思いまする。
甘残りの酒がもてはやされる方が不思議ですわ。
旭若松、随分前に飲んで、甘いなあ(味が)と思った記憶があります。
今度、機会があれば、再度飲んでみようかな。
To こじこじさん
今でも甘い方だと思います。(^^;
ただ、きちんと締まりやキレを感じるようになりましたから、
味が多いだけの酒から脱却したのでは、と。ぜひお試しください。
さぁて、今年の、どれを選びましょうかねぇ。
といいつつ、すでに腹は決まっていたりして♪ (笑)