酒の十徳
室町時代の狂言、“餅酒” には…
- 独居の友
- 万人和合す
- 位なくして貴人と交わる
- 推参に便あり
- 旅行に慈悲あり
- 延命の効あり
- 百薬の長
- 愁いを払う
- 労を助く
- 寒気の衣となる
と酒の十徳が謳われておりますが、同時代に茶道や香道とともに起こったとされる “酒道” は…
酔っ払うことが目的ではない、酒はもっと優雅で素晴らしいものであろう
が基本精神であったものの、明治の中頃には潰えてしまったとか。
幻となった修道なれど、ここに『百薬の長』と『キチガイ水』の境目がありますな。
あ、読みは同じとはいえ、衆道ではありませぬゆえ、早とちりなされませぬよう。(笑)
たとえガクンと凹むことがあった夜であろうと、自棄酒に走っては忌み嫌う『キチガイ水』を是認してしまいまする。
こんな時こそ、己が不甲斐なさを正してもらうためにもまっとうな中でもさらにまっとうな酒を…
初めて登場した竹鶴の割水版生酛はご覧のとおり黒ずくめ♪
開け立てなれど、まずは冷やジュルから…
「うぅむ」と唸ったきり後が続きませぬ。
生酛特有の乳酸の利いた含み香。ビシッと締まった味わいは割水をされても少しも薄まることなく、しっかり最後まで醗酵させた酒でしか到達しない極みとでもいえばいいのでしょうか、こちらの背筋もビシッと伸びますな。
竹鶴ですから遠慮容赦なしに煮たものの、さすがにいきなりはなかった?
すっかり若返ってしまい、硬いわ、渋いわ、往生することになったとはいえ、やや冷めてくると、70%とは思えぬきれいさととんでもない強さを秘めていることに気づかされます。
「酒を知り、己を知る」
決して優雅ではありませんが、たまには堅苦しく酒を呑むのも呑兵衛修行の一つでしょうか? (苦笑)

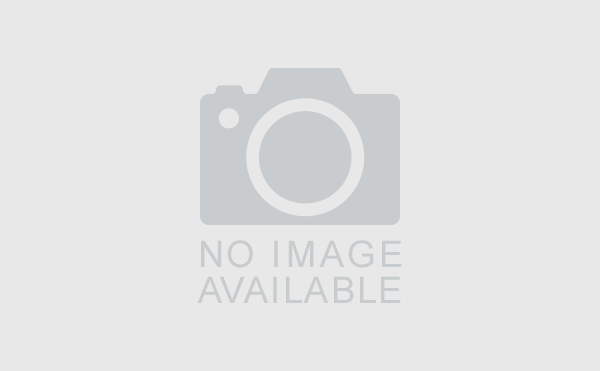
黒鶴、秘密の貯蔵庫に移しました!
一合だけ飲みましたが・・・絶対に手をつけないぞー!あと何年か先までは!
代わりに、どこかお店で出会えるかなぁ・・・?!
To まき子さん
今月からもう次の年度(19BY)が出ているから、また追加しなきゃ♪
どこかのお店…来週末(12/12)、伊奈中央まで行けば呑めるでしょ。(笑)
どうも黒と竹鶴のイメージが合わねえんだよなぁ・・・・
To shootさん
shootさん的には何色?
明日、おでん屋さんへ行くとガッツン酒に会えるはず♪
同じBYの小笹屋との呑み比べも一興ですね。
To ちゃむさん
むしろ一晩中これだけで通したい!! と思うはず。(笑)